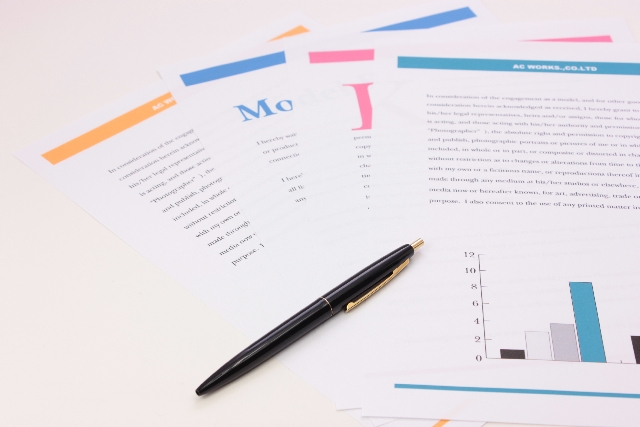


社会保険労務士の業務について詳しい方に質問です。
社会保険労務士の業務内容はどういったものですか?
また、経営者、労働者、どちらの立場に立った資格ですか?
よろしくお願いします。
社会保険労務士の業務内容はどういったものですか?
また、経営者、労働者、どちらの立場に立った資格ですか?
よろしくお願いします。
wikipedeiaより
1.労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成し、その提出に関する手続を代行すること
2.労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
3.個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
4.地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
5.個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が60万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること
6.労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く)を作成すること(1.の書類を除く)
7.事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること
ただし、これらの事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。
1~6の業務は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が原則として他人の求めに応じて報酬を得て行ってはならない。
さらに、3~5の業務については、特定社会保険労務士でなければ行うことができない。
(企業からの依頼による、従業員に対する上記概要範囲における事務処理 )
人事雇用等 労務に関する相談、指導
給与計算
労働災害、通勤災害における申請や給付に関する事務手続き
社会保険における私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付の事務手続き
雇用保険における申請や給付等の事務手続き
労働保険料の加入手続き、年度更新に伴う算定納付諸手続き
社会保険料を確定させる算定基礎届の作成
労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則の作成・改訂
賃金や退職金、企業年金制度の構築
各種助成金の相談、申請
労働安全衛生に関する相談、指導
社員研修、社員教育の実施
メンタルヘルス対策
(個人からの依頼による、上記概要範囲における事務処理 )
年金に伴う相談、給付代行(老齢、遺族、障害、離婚時分割、他人の作成した申請書等の審査)
労働に伴う相談、紛争代理(特定社会保険労務士としての付記が前提)
(行政協力という名目での下記 厚生労働省管轄下の公的機関での相談業務 )
労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、街角の年金相談センター他
<業務形態>
社会保険労務士の業務は、主として企業との顧問契約にある。企業の人事・労務諸問題に関する相談、社会保険・労働保険諸手続きの事務代理・提出代行、給与計算などが主軸となる。又、ファイナンシャル・プランナー資格やDCプランナー、DCアドバイザー資格、モーゲージプランナー資格を併せ持ち、年金・資産運用に関するコンサルタント業を主とする実務家や税理士、中小企業診断士、行政書士といった他士業資格を保有した上で多角的な活動を行う実務家もいる。最近では、労働トラブルの増加に伴い「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、当事者を代理して具体的な解決策を提案するなど労使双方の諍いの解決に尽力する社会保険労務士(裁判外紛争解決手続制度の代理業務を行う場合は、特定社会保険労務士としての付記が必要)も増えている。
社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない。
1.労働及び社会保険に関する諸法令に基づき行政機関(主に労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所)に提出する申請書、届出書、報告書、審査請求書、異議申立書、再審査請求書その他の書類を作成し、その提出に関する手続を代行すること
2.労働社会保険諸法令に基づく申請、届出、報告、審査請求、異議申立て、再審査請求その他の事項(厚生労働省令で定めるものに限る)について、又は当該申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対してする主張若しくは陳述(厚生労働省令で定めるものを除く。)について、代理すること
3.個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律6条1項の紛争調整委員会における同法5条1項のあっせんの手続及び男女雇用機会均等法18条1項、育児介護休業法52条の5第1項 及びパートタイム労働法22条1項の調停の手続について、紛争の当事者を代理すること
4.地方自治法180条の2の規定に基づく都道府県知事の委任を受けて都道府県労働委員会が行う個別労働関係紛争(個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律1条に規定する個別労働関係紛争(労働関係調整法第6条に規定する労働争議に当たる紛争及び特定独立行政法人等の労働関係に関する法律26条1項に規定する紛争並びに労働者の募集及び採用に関する事項についての紛争を除く。)をいう。)に関するあっせんの手続について、紛争の当事者を代理すること
5.個別労働関係紛争(紛争の目的の価額が60万円を超える場合には、弁護士が同一の依頼者から受任しているものに限る)に関する民間紛争解決手続(ADR法2条1号に規定する民間紛争解決手続をいう。)であって、個別労働関係紛争の民間紛争解決手続の業務を公正かつ適確に行うことができると認められる団体として厚生労働大臣が指定するものが行うものについて、紛争の当事者を代理すること
6.労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含み、申請書等を除く)を作成すること(1.の書類を除く)
7.事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること
ただし、これらの事務を行うことが他の法律において制限されている事務並びに労働社会保険諸法令に基づく療養の給付及びこれに相当する給付の費用についてこれらの給付を担当する者のなす請求に関する事務は含まれない。
1~6の業務は、社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者が原則として他人の求めに応じて報酬を得て行ってはならない。
さらに、3~5の業務については、特定社会保険労務士でなければ行うことができない。
(企業からの依頼による、従業員に対する上記概要範囲における事務処理 )
人事雇用等 労務に関する相談、指導
給与計算
労働災害、通勤災害における申請や給付に関する事務手続き
社会保険における私傷病、出産、死亡等に関する申請や給付の事務手続き
雇用保険における申請や給付等の事務手続き
労働保険料の加入手続き、年度更新に伴う算定納付諸手続き
社会保険料を確定させる算定基礎届の作成
労働者名簿及び賃金台帳など法定帳簿の調製、就業規則の作成・改訂
賃金や退職金、企業年金制度の構築
各種助成金の相談、申請
労働安全衛生に関する相談、指導
社員研修、社員教育の実施
メンタルヘルス対策
(個人からの依頼による、上記概要範囲における事務処理 )
年金に伴う相談、給付代行(老齢、遺族、障害、離婚時分割、他人の作成した申請書等の審査)
労働に伴う相談、紛争代理(特定社会保険労務士としての付記が前提)
(行政協力という名目での下記 厚生労働省管轄下の公的機関での相談業務 )
労働基準監督署、ハローワーク、年金事務所、街角の年金相談センター他
<業務形態>
社会保険労務士の業務は、主として企業との顧問契約にある。企業の人事・労務諸問題に関する相談、社会保険・労働保険諸手続きの事務代理・提出代行、給与計算などが主軸となる。又、ファイナンシャル・プランナー資格やDCプランナー、DCアドバイザー資格、モーゲージプランナー資格を併せ持ち、年金・資産運用に関するコンサルタント業を主とする実務家や税理士、中小企業診断士、行政書士といった他士業資格を保有した上で多角的な活動を行う実務家もいる。最近では、労働トラブルの増加に伴い「個別労働紛争の解決の促進に関する法律」に基づき、当事者を代理して具体的な解決策を提案するなど労使双方の諍いの解決に尽力する社会保険労務士(裁判外紛争解決手続制度の代理業務を行う場合は、特定社会保険労務士としての付記が必要)も増えている。
社会保険労務士は、国又は地方公共団体の公務員として職務上取り扱った事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱った事件については、その業務を行ってはならない。
面接を断ろうか迷ってます。
転職して半年、初日から毎日辞めたいと思いながら我慢してきました。
次、良い仕事を見つけてから辞めようと転職サイトで応募した会社から面接の連絡を頂いたん
ですが…
正社員ともパートとも契約社員とも記載がないんですが、給与は時給千円、寸志ありとなっているので契約社員だと思います。
私は田舎住みでろくな求人がないので都市部に仕事を見つけて引っ越す予定ですが、社宅か住宅手当てがあるか聞いたらないとのこと。
時給千円で1日8時間×月21日出勤で計算すると15万ほどにしかならず、そこから社会保険等を引かれたら手取りはさらに減る
その給料でマンションを借りて一人暮らしは到底無理なので面接にいくだけ無駄だと思えてきました。
面接にいくのも往復4時間、交通費6000円ほどかかるし。
面接でいずれ正社員になれる話が出れば別ですが、現状では行くだけ時間とお金の無駄かもなと思っています。
この場合、自分ならどうしますか?
転職して半年、初日から毎日辞めたいと思いながら我慢してきました。
次、良い仕事を見つけてから辞めようと転職サイトで応募した会社から面接の連絡を頂いたん
ですが…
正社員ともパートとも契約社員とも記載がないんですが、給与は時給千円、寸志ありとなっているので契約社員だと思います。
私は田舎住みでろくな求人がないので都市部に仕事を見つけて引っ越す予定ですが、社宅か住宅手当てがあるか聞いたらないとのこと。
時給千円で1日8時間×月21日出勤で計算すると15万ほどにしかならず、そこから社会保険等を引かれたら手取りはさらに減る
その給料でマンションを借りて一人暮らしは到底無理なので面接にいくだけ無駄だと思えてきました。
面接にいくのも往復4時間、交通費6000円ほどかかるし。
面接でいずれ正社員になれる話が出れば別ですが、現状では行くだけ時間とお金の無駄かもなと思っています。
この場合、自分ならどうしますか?
質問者さんが、迷いながらも止めておこうとしているのに賛成です。
手取り15万円でアパート、食費、光熱費、雑費…などを引くと なんも残りません。
年齢がわかりませんが、私なら 慌てずに じっくり探しますね。
それでアンテナは目一杯張ります。やっていらっしゃると思いますが、
ハローワーク、求人専門会社(フロムエーなど)などに登録します。 他に求人専門誌(タウンワーク…)なども隅々までチェックです。
ホームセンター、地元のスーパーなど入り口に求人の張り紙がある場合があります。
参考にして下さい(^^)
<補足>
確かに15万円は厳しいですね。
やっぱり地元でしばらく 辛抱しながらチャンス待つしかないですね。
手取り15万円でアパート、食費、光熱費、雑費…などを引くと なんも残りません。
年齢がわかりませんが、私なら 慌てずに じっくり探しますね。
それでアンテナは目一杯張ります。やっていらっしゃると思いますが、
ハローワーク、求人専門会社(フロムエーなど)などに登録します。 他に求人専門誌(タウンワーク…)なども隅々までチェックです。
ホームセンター、地元のスーパーなど入り口に求人の張り紙がある場合があります。
参考にして下さい(^^)
<補足>
確かに15万円は厳しいですね。
やっぱり地元でしばらく 辛抱しながらチャンス待つしかないですね。
4月20日に突然解雇されたのですが、離職票には一身上の都合による自主退職と書かれ、離職日も3月6日になっています。
会社に問い合わせた所、「よくわからないので調べてみます」で終わったのですが、泣き寝入りだけはしたくないので、どこに相談したら良いか知っている方教えて下さい!
会社に問い合わせた所、「よくわからないので調べてみます」で終わったのですが、泣き寝入りだけはしたくないので、どこに相談したら良いか知っている方教えて下さい!
相談先とこれからの対策をアドバイスします。
① まず、ハローワークへ行き離職票の「自主退職」、離職日が偽りであることを言ってください。
解雇と自主退職では、雇用保険をもらう条件が天と地ほど違います。
② 解雇について
☆解雇の予告
労基法第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、(労基署の承認を得た懲戒解雇を除きます。)次の手続のいずれかをとらなければなりません。
(1) 少なくとも30日前に解雇予告をする。
(2) 30日前に解雇予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う。
☆解雇法理
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
解雇が有効とされるには、次の2つの条件を満たしていなくてはなりません。
・客観的に合理的な理由がること
・社会通念上相当であること
◆「客観的に合理的な理由」とは
「合理的な理由」には、次のようなものが考えられます。
・労働者の能力不足
・労働者の服務規律違反等の不始末
・会社の経営上の必要性によるもの
・会社の解散
・ユニオンショップ協定等の労働協約の定めによるもの
◆「社会通念上相当である」とは
「相当である」とは、解雇の事由と、解雇という処分の間のバランスが取れているということです。
合理的な理由は確かにあるが、解雇までやってしまうのは行き過ぎという場合は、「相当でない」となります。
これの判断基準として、次の点を検討し、判断します。
・就業規則違反があった場合、それを会社が知りながら放置していなかったか、また、適切な注意、指導、監督をしていたか
・本人の不適格性是正のために指導や人事異動等の努力を会社はしたか
・本人の能力不足や勤務態度不良について教育・指導をしたか
・他の処分との均衡は取れているか
・整理解雇の場合、「整理解雇4要件」に則っているか
・解雇に不当・不純な動機はないか
というように、解雇が相当であると認められるには、かなりハードルが高くなっており、簡単に解雇ができないように制限が課されています。
③ 相談先
会社の所在地を管轄する労働基準監督署か労働局総合労働相談コーナーへ相談しましょう。
「あっせん」「調停」という制度があるので利用しましょう。
④ ポイント
・ 4.20予告なしの即日解雇であり、30日分の賃金(1か月の給料ではありません)が請求できます。
・ 4.20までの給料は当然もらえます。
・ 有期雇用であるなら雇用期間満了までの給料も請求できます。期間の定めがなければ、ある程度の給料補償も請求できます。
・ 精神的ショックに対する慰謝料も請求できます。
こんな会社に職場復帰したいとは思わないでしょうから、金銭解決を求めて「調停」を申請しましょう。
⑤ 「調停」が不調になったら
会社が調停に応じなかった場合は、裁判所の労働審判を申し立てましょう。懲戒解雇でない限りは、ほぼ勝てます。
① まず、ハローワークへ行き離職票の「自主退職」、離職日が偽りであることを言ってください。
解雇と自主退職では、雇用保険をもらう条件が天と地ほど違います。
② 解雇について
☆解雇の予告
労基法第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合は、(労基署の承認を得た懲戒解雇を除きます。)次の手続のいずれかをとらなければなりません。
(1) 少なくとも30日前に解雇予告をする。
(2) 30日前に解雇予告をしない場合は、30日分以上の平均賃金を支払う。
☆解雇法理
労働契約法第16条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。
解雇が有効とされるには、次の2つの条件を満たしていなくてはなりません。
・客観的に合理的な理由がること
・社会通念上相当であること
◆「客観的に合理的な理由」とは
「合理的な理由」には、次のようなものが考えられます。
・労働者の能力不足
・労働者の服務規律違反等の不始末
・会社の経営上の必要性によるもの
・会社の解散
・ユニオンショップ協定等の労働協約の定めによるもの
◆「社会通念上相当である」とは
「相当である」とは、解雇の事由と、解雇という処分の間のバランスが取れているということです。
合理的な理由は確かにあるが、解雇までやってしまうのは行き過ぎという場合は、「相当でない」となります。
これの判断基準として、次の点を検討し、判断します。
・就業規則違反があった場合、それを会社が知りながら放置していなかったか、また、適切な注意、指導、監督をしていたか
・本人の不適格性是正のために指導や人事異動等の努力を会社はしたか
・本人の能力不足や勤務態度不良について教育・指導をしたか
・他の処分との均衡は取れているか
・整理解雇の場合、「整理解雇4要件」に則っているか
・解雇に不当・不純な動機はないか
というように、解雇が相当であると認められるには、かなりハードルが高くなっており、簡単に解雇ができないように制限が課されています。
③ 相談先
会社の所在地を管轄する労働基準監督署か労働局総合労働相談コーナーへ相談しましょう。
「あっせん」「調停」という制度があるので利用しましょう。
④ ポイント
・ 4.20予告なしの即日解雇であり、30日分の賃金(1か月の給料ではありません)が請求できます。
・ 4.20までの給料は当然もらえます。
・ 有期雇用であるなら雇用期間満了までの給料も請求できます。期間の定めがなければ、ある程度の給料補償も請求できます。
・ 精神的ショックに対する慰謝料も請求できます。
こんな会社に職場復帰したいとは思わないでしょうから、金銭解決を求めて「調停」を申請しましょう。
⑤ 「調停」が不調になったら
会社が調停に応じなかった場合は、裁判所の労働審判を申し立てましょう。懲戒解雇でない限りは、ほぼ勝てます。
関連する情報